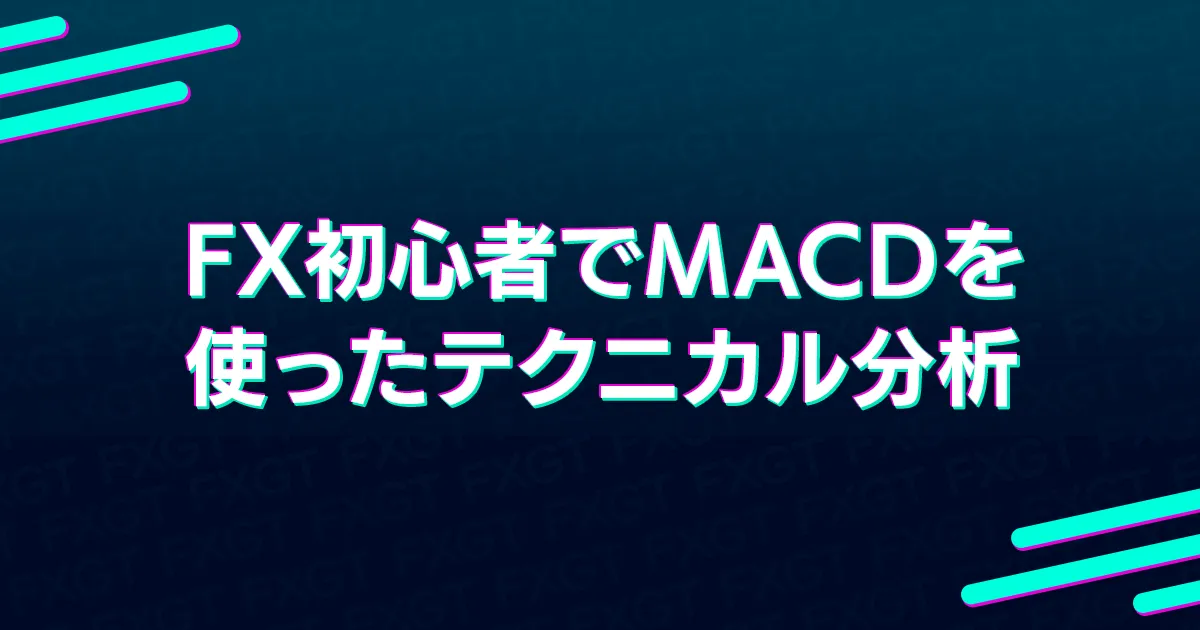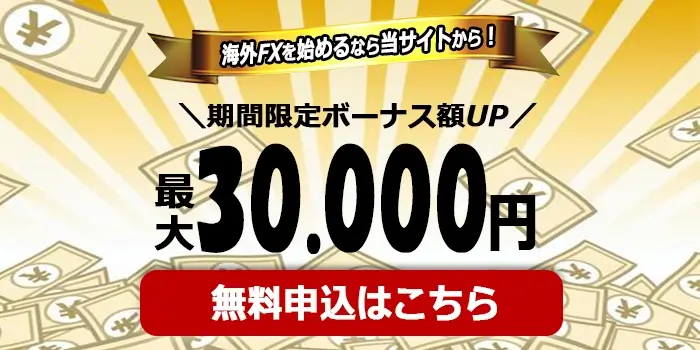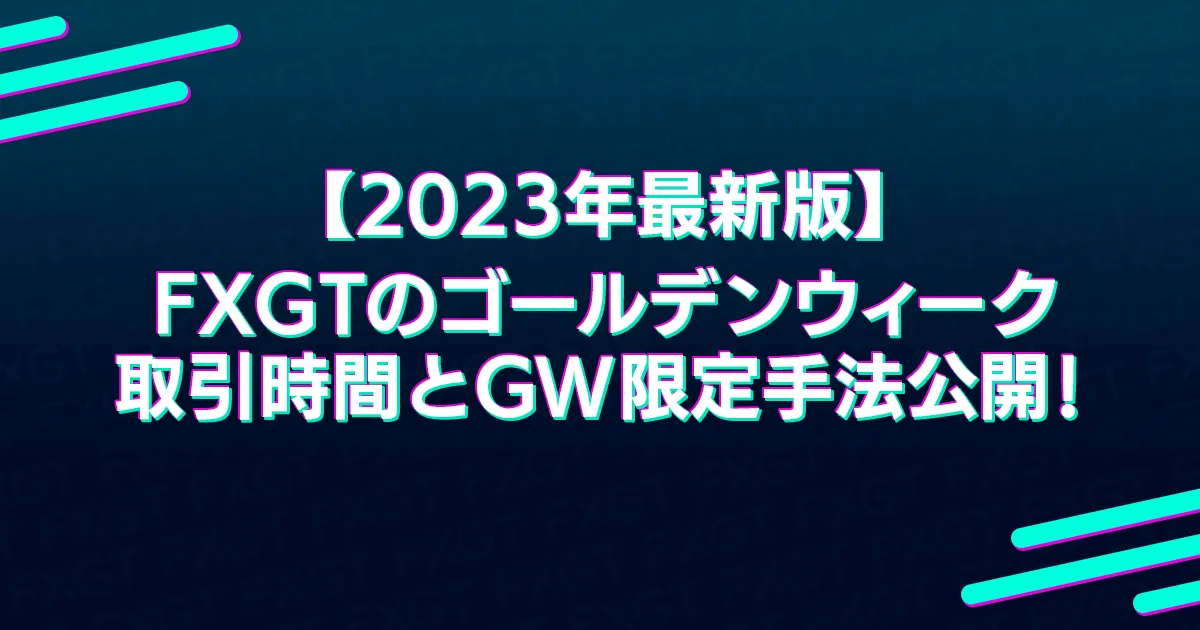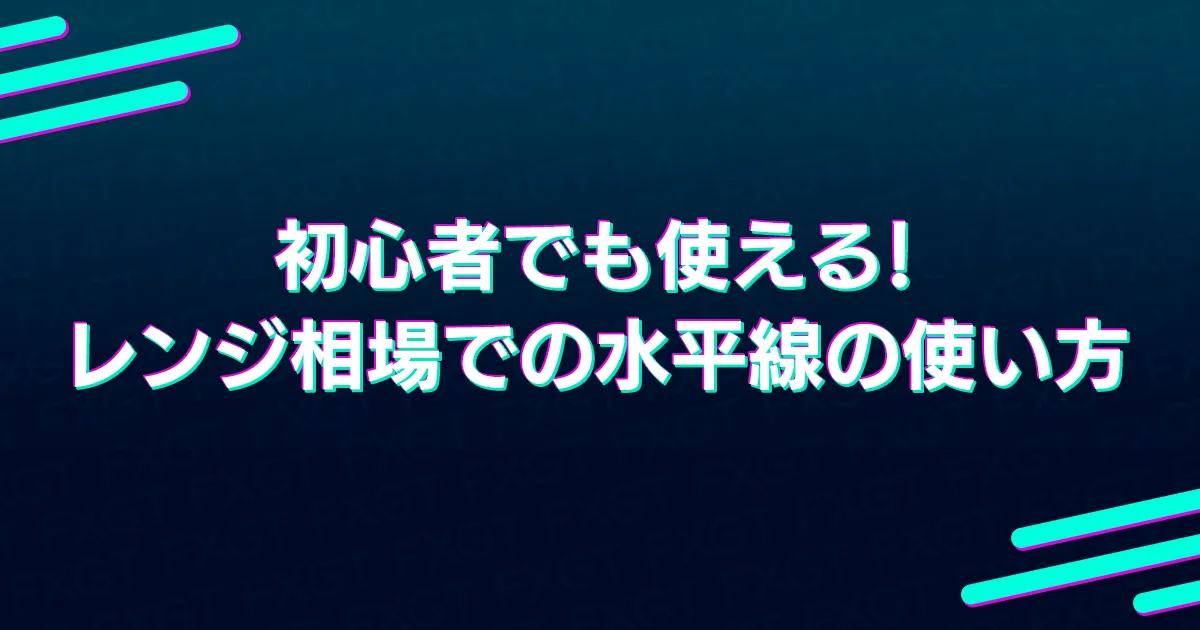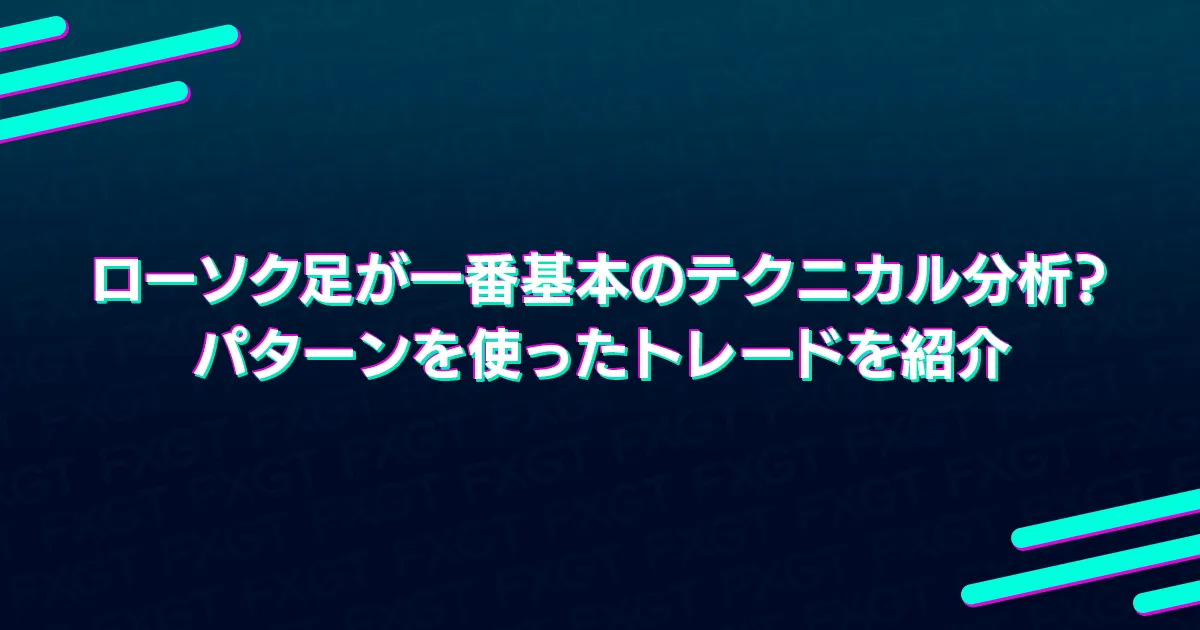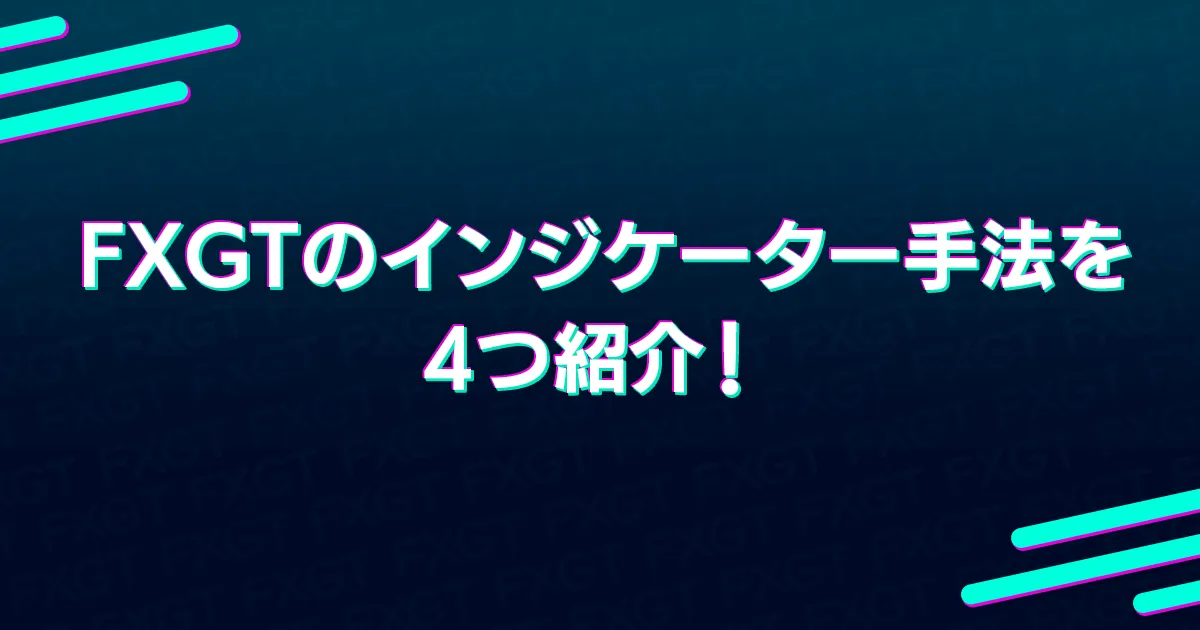「MACDが使いやすいって聞いたけど、どうやって使うんだろう?」
「MACD使ってるけど全然勝てない・・・」
「MACDを使ってどうやって利益を出せばいんだろう?」
と悩んでいませんか。
FX初心者に人気テクニカル分析として使われるMACD(マックディー)、使いやすさに定評がありますが、実は正しい使い方を覚えずにトレードをしているなんてことも。
MACDは使い方や特徴をきちんと理解しておけば、FX初心者でもしっかりとトレードに役立てる分析です。
特に重要なのが、MACDはどのようなタイミングで使えばいいのかであり、ここを覚えればトレードの勝率に反映することができるでしょう。
そこで今回は
- MACDはオシレーター系のテクニカル分析
- MACDを使う基本の分析とダイバージェンスのトレード方法を紹介
- MACDを使う際の注意ポイント
MACDについて基礎から使い方まできちんと理解できるように紹介していきます。
MACDを使いたい、MACDで勝てるようになりたいと考える人は、ぜひ最後までご覧ください。
MACDはオシレーター系のテクニカル分析
MACD(マックディー)とは、Moving Average Convergence Divergenceの略称で、オシレーター系のテクニカル分析です。
短期と中長期による2種類の指数平滑移動平均線(EMA)を使った分析で、2本の線の位置やクロスサインによって、トレンド転換や売買のタイミングを掴めます。
特にトレードを始める際のエントリーのタイミングを掴んだり、利確ポイントを明確にするために使われることが多いです。
それと、チャートとMACDの動きが同期しなくなるダイバージェンスと呼ばれる現象もあり、発生後には激しい値動きが起こることもあるため、使う上で覚えておく重要ポイントです。
ちなみに、MACDはオシレーター系のテクニカル分析ではありますが、移動平均線を使った分析でトレンド把握にも役立てられるため、トレンド系と呼ばれることもあります。
テクニカル分析はトレンド系とオシレーター系に分類される
テクニカル分析には、オシレーター系とトレンド系の2種類が存在します。
オシレーター系とは、相場の買われ過ぎや売られ過ぎを判断できる分析で、一定の振り幅(数値間)を振り子のように行ったり来たりする描写が多いです。
トレンド系とは、相場の方向性を判断できる分析で、買いが続く上昇トレンドなのか売りが続く下降トレンドなのかを知ることができます。
- オシレーター系:MACD、RSI、ストキャスティクス
- トレンド系:移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表
MACDを使う基本の分析とダイバージェンスのトレード方法を紹介
ここからは実際に、MACDの使い方やダイバージェンスについて画像付きで紹介していきます。
- MACDの基本的なトレードでの使い方
- MACDのゴールデンクロス
- MACDのデッドクロス
- MACDのダイバージェンスを使ったトレード方法
- MACDのヒドゥンダイバージェンスを使ったトレード方法
それぞれ詳しく見てみましょう。
MACDの基本的なトレードでの使い方

こちら、MACDを表示させた米ドル円15分足のチャートです。
まずはMACDの基本情報から紹介します。
チャート下の白枠で囲まれた部分がMACDとなります。
- ゼロライン
- MACD線
- ヒストグラム
MACDは2本の指数平滑移動平均線から構成されており、青色の短期線をMACD、赤色の中長期線をシグナルと呼び、中心をゼロラインと呼び、上の+数値側がプラス圏で下の-数値側をマイナス圏と判断します。
中央の棒グラフはMACDヒストグラムと呼び、MACDの線よりも早く相場の状況を判断できるように作られたもので、ツールによっては表示されない場合もあります。
ヒストグラムはMACD線よりも早く棒グラフの減少や増加でトレンド転換のサインを認知できますが、反応が早いためダマシが発生することもあり、信頼度がMACD線よりも低い点には注意しましょう。
次に実際のトレードでエントリーに使える方法を紹介していきます。
MACDのゴールデンクロス
MACDの一般的な使い方は、2本の線がクロスした際のゴールデンクロスとデッドクロスサインでトレードを行います。
青線MACDが赤線シグナルを下から上に突き抜けたサインをゴールデンクロスと呼び、上昇が起こるサインとして判断し、買いを狙ったトレードが行えます。
先ほどのチャートの②がゴールデンクロスに該当し、サインが出た瞬間にエントリーをすることで上昇トレンドの波を掴んだトレードができます。
下降トレンドから上昇トレンドへの転換を狙うことが多く、ゼロラインより下側のマイナス圏で発生した際には力強い上昇が起こります。
上側のプラス圏で発生した場合にはそこまで強い上昇が起きないことが多いです。
MACDのデッドクロス

逆に青線MACDが赤線シグナルを上から下に突き抜けたサインをデッドクロスと呼び、下降が起こるサインとして判断し、売りを狙ったトレードが行えます。
上昇トレンドから下降トレンドへの転換を狙うことが多く、ゼロラインより上側のプラス圏で発生した際には力強い下降が起こります。
下側のマイナス圏で発生した場合にはそこまで強い下降が起きないことが多いです。
下降トレンド中にゴールデンクロスが発生したタイミングで買いのエントリ、上昇トレンドに転換後から上昇が続き、デッドクロスが発生もしくは発生しそうなタイミングで利確を行うといったトレードができます。
ゴールデンクロスやデッドクロス、ダマシなどについては「FXGTおすすめの移動平均線を使ったテクニカル分析|ゴールデンクロスとデッドクロス」の記事でも詳しく紹介しているので、よければそちらも参考にしてみてください。
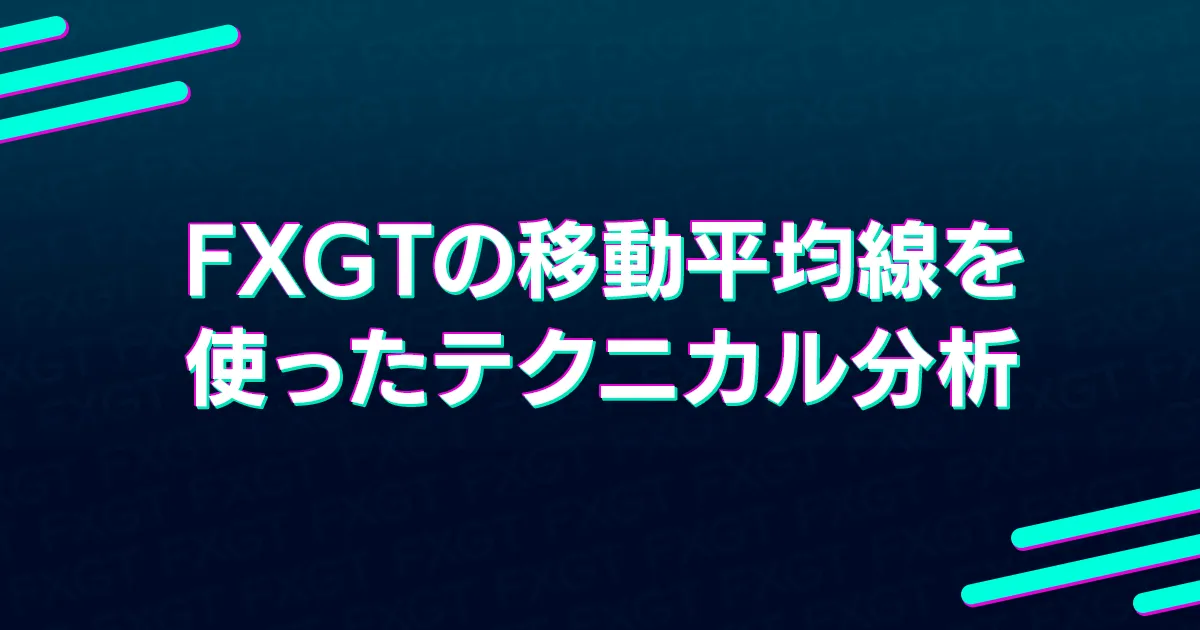
MACDのダイバージェンスを使ったトレード方法

ダイバージェンスはチャートとMACDの逆行現象のことで発生すると、トレンド転換から大きな上昇や下降が発生します。
通常のMACDはチャートの買いと売りの強さを表現するため、上昇が続けばMACDも上昇し下降が続けばMACDも下降しますが、ダイバージェンスはチャートと逆の動きをMACDがします。
上のチャートでは上昇が発生していますがMACDは上がらず緩やかに下がっており、この状態がダイバージェンスであり、その後チャートは大きく下げていきました。
ダイバージェンスが発生すると現在とは逆のトレンドに大きく動くため、発見したらMACDのゴールデンクロスやデッドクロスのタイミングを見計らってエントリーすると、大きく値幅を取ることができます。
MACDのヒドゥンダイバージェンスを使ったトレード方法

ヒドゥンダイバージェンスは、逆行現象でもトレンド継続を示唆するサインです。
上昇トレンド中ではチャートは安値を切り上げながらトレンドを形成しますが、MACDは安値を切り下げながら動いていきます。
逆に下降トレンド中はチャートは高値を切り下げながらトレンドを形成しますが、MACDは安値を切り上げながら動いていきます。
ヒドゥンダイバージェンスを見つけることができれば、トレンドはまだ続くと判断できるため、トレードが続く方向でゴールデンクロスやデッドクロスを見つけてエントリーするとよいでしょう。
MACDを使う際の注意ポイント
MACDの使い方を紹介してきましたが、実際にトレードを行う上での注意すべきポイントも存在します。
- オシレーター系でもレンジ相場には弱い
- 単体よりも組み合わせることで分析の信頼性を上げる
しっかりとポイントを抑えて、トレードに活かせるようにしましょう。
オシレーター系でもレンジ相場には弱い
MACDはオシレーター系でも移動平均線を使ったテクニカル分析なので、トレンド相場に強い性質を持ちます。
逆に一定の値幅を行ったり来たりするレンジ相場には弱いため、上手く使えないことが多いです。
そのため、レンジ相場ではMACDを無理に使おうとせず、トレンド発生中に使うことをおすすめします。
単体よりも組み合わせることで分析の信頼性を上げる
MACDはテクニカル分析の中でもチャートの動きに敏感で反応が早いことから、サインが出ても上手く機能しないダマシが発生しやすいです。
単体では少し信頼度に欠けるため、他のテクニカル分析と組み合わせて使うのがおすすめです。
よく使われる組み合わせとしてはMACD×RSIがあり、MACDのゴールデンクロスやデッドクロスのサインをRSIの売られ過ぎと買われ過ぎのサインで補助して、サインの信頼性を上げられます。
このように他のテクニカル分析と組み合わせることで信頼性を高められるため、使いやすく分析を見つけてオリジナルの組み合わせを探してみましょう。
まとめ:まずはチャートに導入してMACDの動きを確かめてみよう
今回は、「FX初心者におすすめのMACDを使ったテクニカル分析|基本と使い方について」というテーマで紹介してきました。
MACDはゴールデンクロスやデッドクロスのエントリーに使いやすいサインが分かりやすく、ダイバージェンスは大きな値動きを掴めるサインとしても使えるため初心者におすすめです。
当サイトでは、初心者が使いやすいテクニカル分析を他にも詳しく紹介しているので、ぜひテクニカル分析探しをされている方は別の記事も参考にしてください。